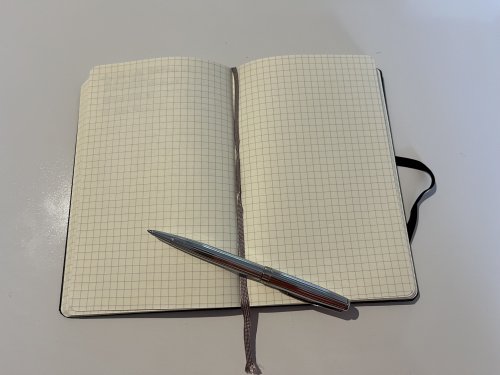
ところが、最近、ノートにメモを書こうとすると、悲しいくらい字が汚いのです。何が、おかしくなったのかというと、字を急いで書いてしまって、殴り書きのようになってしまうのです。物事を考えるスピードはキーボードで文字を打つスピードに影響されているようで、それを手で書こうとすると、考えるスピードとうまく噛み合わなくなってしまうのです。なんかキーボードを打つのと同じ速さで字を書かないといけないという強迫観念に苛まれている感じです。
でも、オーストラリアの大学で学んでいる留学生たちのノートや教科書を見せてもらうと、びっしりと手書きで綺麗な文字が書かれています。それらを見ていると、じっくりと理解しながら、特に外国語で、物事を深く理解していくための学ぶスピードは、手書きのスピードにフィットしているのではないかと感じたのです。
経営という仕事は、生産性とか効率性とは違った、深く考えることの質を問われていると思います。だからこそ、今年は留学生たちのように、じっくりと考えたアイデアたちを、手書きの読みやすい文字で、ノートにまとめていこうと考えています。










