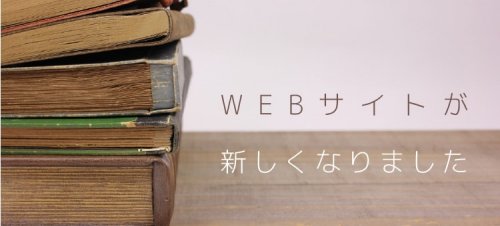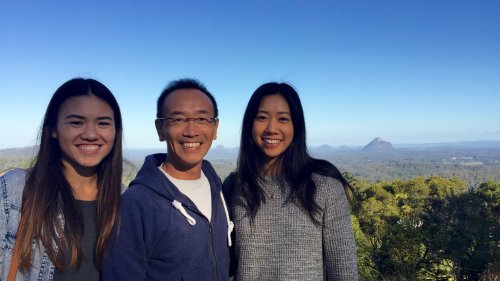僕たちが車で旅をスタート出来た一つの理由はAirbnbの存在です。ホテルよりもずっと安く、モーテルよりもずっと快適に過ごせるのがAirbnbです。出来るだけ、今まで住んでいたアパートの家賃並みの宿泊費で滞在できるようには考えていて、都市では少し値段が高めでも便利な場所、田舎では値段を抑えてなど工夫して、トータルでバランスを取っています。
今まで、サンシャインコーストとブリスベンのホストの家に滞在しましたが、こんな感じの場所でした。



ここからはブリスベンの空港の近くの家



それぞれ、数日過ごすには十分な部屋でしたし、朝ごはんはシリアルやヨーグルトやフルーツがついていて、外に買いに行く必要がありませんでした。
留学生たちにとって、渡航後、最初に滞在する場所はホームステイ、学生寮、バックパッカーなどの安い宿などの選択肢しかありませんでした。しかし、これからはAirbnbも選択肢の一つとして考えるべきだと思います。もちろん、予約に関しては自分ですべて手配をしなくてはいけませんが、オーストラリア以外でも留学を経験をされた方や、海外旅行などですでにAirbnbに滞在した経験がある方は、抵抗なく滞在ができると思います。そして、学校や新しい街に慣れた頃に、友人たちの情報を使いながらシェアハウスに移動すればいいのです。
どんな家庭に振り分けられるかわからないホームステイ、どんなルームメートがいるのかわからない学生寮、そのようなことがリスクだと感じ、どんなことでも自分で選んでみたい少しわがままなタイプの人は、滞在先についても自分でコントロールしてみることをお勧めします。しかし、もし、何かトラブルがあってもそれも自分で解決していかなくてはならないということはお忘れなく。だけど、そんなトラブルも(今のところ、何も僕にはトラブルは起きていませんが)きっと自分で解決することで成長できるのだと思います。